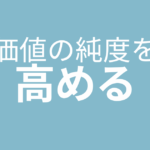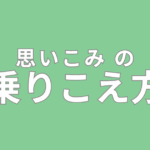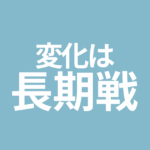4章|スキル長期活用法|ゴール更新をつづけよう
無意識を変化させる2つのこと
意識を整える3つのこと
3-1(自問自答)の補足
▹ 現在の記事:4-1(人生カテゴリー)の補足
この記事でわかること:ゴールは「1つ」でなくていい
- 人生を俯瞰して複数のゴールを持てば、モチベーションに好影響
- お互いに矛盾するゴールがあってもOK、それぞれを高く遠くへ設定
- Want toを拡大すれば面倒なことも自然とこなす
ゴール設定は複数の分野で
📘 人生カテゴリーのツールを活用する際は、複数の領域で並行してゴールを設定するのが効果的です。プラスの価値が増えていくと、ゴールが複数あってもより抽象度や臨場感の高いものに芋づる式に引き寄せられ、中身がまとまってきます。
ゴール同士が葛藤してもOK
異なる領域のゴール同士が矛盾することもあるかもしれませんが、それを気にする必要はありません。たとえば…
・「自宅のアトリエで365日油絵に没頭する人生」
・「365日世界中を旅する人生」
このように、現実的に両立が難しい矛盾があっても、問題ありません。どの領域でも「高望み」することで、プラスの価値が個人の枠を超えて、やがて人類共通のゴールへとつながっていくからです。
ゴールを平行すると、「燃え尽き」も防ぐ
人生を俯瞰の視点で捉えることには、もう一つ重要な意味があります。たとえば…
・仕事一筋で生きてきた人が、定年退職後に生きがいを失い体調を崩すケース
・子どもの頃からオリンピックを目指し、見事に金メダルを獲得したものの、その後燃え尽きてしまうケース
これらは、一つのゴールしか持たず、平行して他のゴールを設定してこなかったことが原因のひとつです。
ゴールはいくつあっても良いものですし、どんなゴールを設定するかも自由です。ゴールを、常日ごろから複数持ち平行させることで、「Want to」の感情を満たしておきます。そうすることで、仮に何かを失ったりつまずいたりしても、新しい道を見つけやすくなります。第二の人生、第三の人生とつづきやすくさせてくれるのです。
また、平行してゴールを設定することで、「どの未来を選ぶか」「未来に何を意図するのか」の練習にもなります。ゴール設定は、想像するだけで始められるため、やらない理由はないと言えます。
ゴール設定は高く、遠く
新しいテーマをゴールに設定したいときには、その道で成功している人に注目するのは自然なことですが、どんな道にも「突き抜けた能力を持つ人」は存在します。上を見たらきりがない程ですので、今の自分と比較して、「憧れを通り越して絶望するほどすごい人」をゴール設定の参考にするのも、一つの方法としておすすめします。
ゴールは「ポジティブであればあるほど」「高ければ高いほど」「遠ければ遠いほど」「大きければ大きいほど」力になる、とお伝えしてきました。それは、ゴールの規模がそのままモチベーションの大きさに直結するからです。
また、高いゴールを設定することで、途中にある小さな目標が「単なる通過点」となり、結果的に成果が出やすくなります。たとえば…
・「ほどほどのゴール」を設定すれば、手を抜いても達成できるかもしれませんが、本気を出す必要がなくモチベーションや持続力もそれなり
・「超ポジティブ出世のゴール」を目指せば、本気度もモチベーションも持続力も高く「ほどほどゴール」など余裕で達成してしまいます。
つまり、「その先」のビジョンを常に見続けることが、モチベーションも持続力も枯れさせない秘訣なのです。達成したときの嬉しさやプロセスの楽しさにも差があります。
人生のいくつかの領域で並行してゴール設定をすると、人生全体のモチベーションが高まり、価値が増えながら自分らしいバランスに最適化されていきます。その結果…
・情熱
・思い
・生きがい
といった本質的な感情が、より身近なものになるでしょう。「楽しい」「好き」などのポジティブ感情を優先することで「やらされ感」は減る方向になります。
目的は「Want to」を取り戻し、拡大すること
もし、ゴール達成のプロセスが「面倒」とか「苦痛」などネガティブに感じる場合、無意識が「変化に抵抗している」サインかもしれません。そんなときは、本メソッドの目的を思い出してください…
・自分のためになる
・周りの人/世の中のためにもなる
・やりたいことをやる
・自分らしくご機嫌でいる
・いくつになっても成長する
本メソッドは、「やらされること(Have to)」を増やすためのものではありせん。ゴール達成の過程で「達成に不利なネガティブ感情や思い込み」を乗り越えれば、最終的には「楽しい」や、「好き」の感情だけが残り、増えていってくれます。正確に言えば、本来持っていた「Want to」を「取り戻す」ということです。
「Have to」には自然と向き合うようになる
Want toだけが残るとは言いましたが、そもそも本書の趣旨はモチベーションの管理と促進です。実際のところ、モチベーションは強制の意味を含む言葉ですし、世の中「やりたいことをやるには、やりたくないことも避けられない」現実があり、そこにはリスクも責任も伴います。ですが、本書の方法でWant to が拡大されると、目先の面倒なことや、やりたくないことでも「ついついできてしまう」状態になる可能性があります。すぐにそうなるとは限りませんが、理論的にそうなる構造になっています。
常に「その先」に魅力的なゴールが「見えて」いるようになるなら…
・グズグズやる
・のらりくらり先延ばし
・グダグダになる
・嫌々やる
・拒絶する
・振り回される
・時間に追われる
といった状態が自然と減っていくでしょう。「やった方が早い」と思えるようになり、前向きな行動が習慣化されていものと思います。
仕事のやめ時
もし、仕事を辞めたいと思ったときは、衝動的に決断せず、会社のゴールやビジョンよりも、はるか大きく高く遠くにまで個人的ゴールを拡大してからにしてください。そのための必要十分な時間をとりましょう。そのアファメーションを実行しながら、何が起こるかを見届けてから判断するのでも遅くはありません。
どうせ辞めるなら…
・モチベーションの高い状態で辞める
・自分のゴールを明確にした上で、新しい道を選ぶ
この方が、どの選択をするにしてもスムーズに結果につながるでしょう。辞めるのも新しいことをするのも労力ですし、自分のゴールを持っている方がどんなプロセスもうまくいきます。また、自己評価や他者からの評価も向上し、悪い結果にはつながりにくくなります。
🔹 前のページ:「3-1 人生…の補足」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
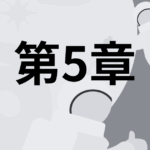
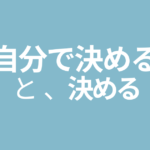
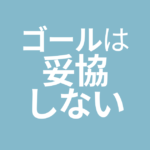
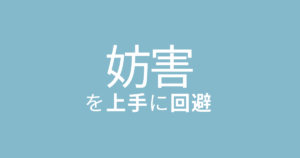
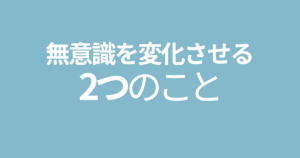
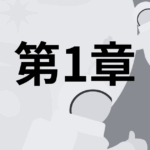
![[3-1] 自問自答で夢を深掘り](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/3-1-150x150.png)