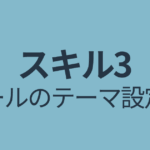人生の俯瞰的視点の活用で、ブレないゴールに
📘 私達は、どんなタイミングで自分の人生を俯瞰するでしょうか?
・人生の節目や転機で立ち止まりたいとき
・過去/現在の成果を振り返るとき
・将来の予定や計画を立てるとき
・何か新しいことを始めたいとき
・未来を予測しようとする
このような瞬間に、人生を広い視点で見直すことが多いのではないでしょうか。本メソッドでは、こういった視点をもっと頻繁に、日常的に、長期的に活用することが効果的だと考えます。
俯瞰的なゴール設定を意識しないと、目の前の出来事に流されて視野が狭くなりがちです。ゴール設定を習慣化するには「人生全体を俯瞰する視点」を定期的に持つことが重要です。人生を俯瞰する目的は下記のようなものがあります…
・「味/関心/楽しみ/好きなことなど(Want to)」にテーマを絞るため
・さまざまな視点を意識し、モチベーションの起点を増やすため
・結果へ相乗効果を出し、より良い結果へつなげるため
・ポジティブ感情の起点を増やすため
・複数のゴールを同時に設定するため
これらはすべて…
・人生の主人公として主導権を握る
・バランスを目指す
・視野を高く広く保つ
ことにつながります。
人生を俯瞰するための10の視点
人生を俯瞰するとき、下記のような10のカテゴリーに分けて考えてみましょう。
(以下あいうえお順)
1家族
2身体の健康
3経済
4心の健康
5コミュニティ
6生涯学習
7職業
8人間関係
9プライベート
10余暇
このように項目を分けることで、ゴール設定の際のたたき台になります。必ず10個にする必要はなく、自分に合った数に調整して構いません。また、カテゴリー名も自分がしっくりくる言葉に言い換えるのがベストです。
いくつかのカテゴリーを設定したら、そのカテゴリー数のそれぞれで、「自分が興味/関心を持つこと/もの」を洗い出してみましょう。10個なら、価値観のヒントや可能性は×10になり、見つかりやすさも×10、ポジティブ感情の起点も×10になります。そのため、最低でも8つ以上のカテゴリーを設定することをおすすめします。
「あなたのゴールは何ですか?」と突然聞かれても、白紙の状態では答えにくいものですが、カテゴリーごとに分けて考えれば、自分の意見やゴール、価値観が整理しやすくなります。長期で使えば、ゴールの情報量が増え、内容も充実し、仕事だけでなく、人生全体の主導権を握るきっかけになります。
ここで注意したいのは、カテゴリーは固定された概念ですとは言っていないことです。カテゴリー自体がゴールではないのです。カテゴリーは、ゴール設定のための手段にすぎません。
【人生カテゴリーの例】
8~12種類のカテゴリー例をいくつか紹介します。参考にしながら、自分に合った分類を考えてみてください。
《3カテゴリーの場合》
1経済
2健康
3社会性
《4カテゴリーの場合》
1関係性
2経済
3健康
4仕事
《6カテゴリーの場合》
1経済
2健康
3社会性
4趣味
5職業
6人間関係
《8カテゴリーの場合》
1引退後
2経済
3健康
4自己成長
5社会貢献
6趣味
7職業
8関係性
《12カテゴリーの場合》
1引退後
2家族
3関係性
4経済
5健康
6社会貢献
7趣味
8生涯学習
9職業
10精神性
11プライベート
12余暇
まずは紙やスマホなどに書き出し、自分に合った分類を見つけましょう。数にこだわる必要はなく、考えるための材料として活用してください。
「職業/仕事」と「お金/経済」は性質が違うので、分けて考えましょう。お金のない世界でも自分の仕事は存在します。お金のためではなく、純粋にやりたい仕事もあります。
ちなみに、アリの社会には働かない個体が一定数います。これは、集団としての余力や余裕を保つため、予備的な存在として機能しています。「仕事をしないこ」とも、場合によっては重要な役割のひとつだと言えます。
また、自分にとっては趣味であっても、それを通じてお金を受け取っている場合は、「職業/仕事」のカテゴリーに分類されます。
【ゴールがすでに決まっている人の活用法】
もし、すでに「これだ」というゴールが決まっている場合は、下記のような視点で活用できます。
・ほかカテゴリーを組み合わせることで、もっと素晴らしいゴールにならないか?
・現在のゴールは、ほかのカテゴリーとどのように関連しているか?
・ほかのカテゴリーで、まだ気づいていない可能性はないか?
ゴール達成に向けて動いているうちに、関連するゴール同士がまとまり、新たなカテゴリーが生まれることもあります。すると、次のゴールが見えやすくなるでしょう。
既に決まっているゴールの中身を濃くしていき
↓
視野が広く保たれて
↓
さらにゴールの中身が濃くなる
と、良い循環が起こります。ゴールに対し納得感や確信も深まります。
人生カテゴリー自体が、目指すゴールなのではありません。「自分のゴールが先に存在」して、カテゴリーは後からついてくるものです。
【ゴールがまだ決まっていない人の活用法】
ゴールがまだ明確でない場合は、下記のような問いを考えてみましょう。
・自分にとってWant toであり、課題度/挑戦の度合い/やりがいなどが最大になるのは、どのカテゴリーか?
・圧倒的にポジティブなセルフイメージを持ちやすいのは、どのカテゴリーのゴールか?
・今の自分にとって、最もゴールを設定の必要性が高いカテゴリーは?
・過去に設定してきたゴールには、どのような傾向があるか?
・自分らしさや能力、行動力を発揮しやすいカテゴリーは?
・直感的に興味を持つのはどのカテゴリーか?
これらの問を通して、ゴールのテーマを明確にしていきましょう。
何度もお伝えしますが、ゴールは自分で設定するものなので、カテゴリーは固定されていません。自分なりの分類加減で大丈夫です。
興味/関心ごとや必要性に素直に従いながら、自分のゴールについて情報を集め、知識を吸収し、経験を積むための基盤として活用してください。ただし、カテゴリーに当てはめてから、ゴールを設定するのではなく、まずゴールの焦点やポイントを明確にし、その後で適したカテゴリー名を割り当てるのが理想的です。ゴールの内容は自由なので、カテゴリーそのものがゴールではないことを、忘れないでください。
ゴールについて俯瞰的視点を持ち、スキルを平行して活用することで、モチベーションの起点となる、心に火が付くようなゴールを見つけやすくなります。
では、人生を構成するカテゴリーを10個に分けるとしたら、どのようなものが考えられるでしょうか?例を挙げてみます。
1家族
家庭/婚姻関係/親子関係/兄弟関係/パートナーシップ/師と呼べる人
2身体の健康
健康状態/健康維持/健康管理/衣/食/住/睡眠/通勤環境
3経済
収入/資産/財産/ファイナンス
4心の健康
心の安定/精神性/信仰
5コミュニティ
社会性/公共性/地域、社会、世界との関係性/無償の貢献
6生涯学習
教育/能力開発/自己成長/学び
7職業
仕事/キャリア/ライフワーク/経歴
8人間関係
知人/友人/仲間/親戚など
9プライベート
自分のこと/自分の時間/個人的なこと/自己実現/引退後の夢
10余暇
休養/趣味/楽しみ/娯楽/レジャー
学生の方は、学業を生涯学習や職業としてカテゴリーに含めても良いでしょう。視点が多いほど、人生を幅広く俯瞰するのに役立ちます。
例えば、朝から晩まで仕事に追われていると、とプライベートの時間が不足し、健康や家庭などに悪影響を及ぼしかねません。また、夢ばかりを追いかけて現実への対応や責任を後回しにすると、生活のバランスが崩れることがあります。
現実に向き合う力が湧かないときは、スキル1が有効です。一方で、目の前の現実対応ばかりに意識が向いているときは、スキル1から2まで続けての活用が役立つでしょう。
人生のカテゴリーは、一言で言えば「人生」。どれも、密接に関わり合っています。意識するだけで結果が変わっていくため。意識するだけで結果が変わっていくため、俯瞰的視点を持つことは重要です。
例えば、「趣味/余暇」の分野をひとつのカテゴリーとしてまとめることで、より挑戦的で高いゴールを設定しやすくなります。「無償の貢献こそが自分のライフワークだ」と考える人にとっては、ライフワークと無償の貢献は別の概念ではないはずです。また、「身体の健康」と「心の健康」が密接に関係しているのは明らかです。同様に、「自分との関係」「家族との関係」「ほかの対人関係」「コミュニティとの関係」なども、すべてを1つのカテゴリーとして束ねることもできます。リーダーシップを重視するなら、「社会貢献的要素」「ファイナンス」「休養」「家族」といった要素を束ねてゴールを設定し、バランスを考慮するのも一つの方法です。
繰り返しになりますが、人生を俯瞰する視点は、あくまで「自分にとってのプラスの価値が最大化するゴールを設定するための手段」にすぎません。ゴールを達成し、次のゴールを定めるまでの間も、思考の整理に役立ちます。思考の焦点によって、達成の度合いによっても、カテゴリーを束ねたりバラしたりと変化していきます。そのため、定期的に見直すことが重要です。
最も便利なカテゴリーの種類や数は、目的やその人の状況によって用途によって異なります。
《俯瞰的視点を持つメリット》
・どの人生領域をポジティブへ向けたいか、意識化と言語化を助けてくれる
・もっと多くを望み、自分に高い目標を許可するための基盤にする
・選択肢を網羅的に整理し、ゴールの土台を明確にできる吟味できる
・見落としや盲点をなくし、バランスを整えられる
・モチベーションのポイントを発見しやすくなる
・人生全体の価値の最大化する方向へ向かう
・知識や情報の収集がしやすくなる
・ゴール設定時の指針(羅針盤)になる
・経験値を上げるための基盤になる
・ゴール更新がしやすい
・ゴールの新鮮さを保つ
スキル1~6を繰り返し活用することで、視点の抽象度が上がり、行動や達成を通じて価値ある体験が積み重なっていきます。人生カテゴリーの中身の最適化が進み、ゴールの純度が上がっていきます。
人生カテゴリーを使ってゴールを考える際も、スキル2で紹介した下記ルールを引きつづき、忘れないようにしましょう。
・よりポジティブで、ギャップが大きく、遠く、高い目標ほど効果的なゴール
・何をどうやったら実現できるかわからないが、できるとしたらうれしい
・一見他人事に思えるほどギャップがあるが、より自分らしい在り方
・いまの自分とは異質なようでいて、本音では望んでいる在り方
・手が届きそうになく、一度は諦めたり封印したりした価値観
・不安を感じるが、絶対に失敗しないならやりたいこと
・実現したら心の底からうれしい「Want to」である
・過去の延長線上にはないが、とても自分らしい
・現状の自分の枠をはるかに超えるが、本質的
・納得感や一致感が高く、やらされ感がない
・身近ではないけれど、最高に魅力的
・諦めたくない
・とんでもない
・突き抜けた
・桁外れの
・卓越した
・挑戦的
・野心的
・圧倒的
・高尚な
・情熱的
・魅力的
・飛躍的
・劇的な
これらのルールを意識しながら人生カテゴリーを活用すると、新たな視点が生まれ、次のゴールや新しいセルフイメージのための情報収集がスムーズになります。すると、特に重要な1~3個の人生領域に価値が集約されていくことに気づくでしょう。情報や知識が最適化/抽象化され、ゴールの追求も調子づいてきます。自分の「Want to」「好き」「楽しい」「得意」に目を向ける時間が増え、人生全体を巻き込みながらモチベーションがつづきやすくなります。
私達がふだん持っている思い込み(言葉/セルフトーク)は、安定をもたらしてくれている一方で、行動や思考を制限することもあります。ですが、「自分が経験していないこと、知らないことは無数にあり、その中に自分でも気づかなかったモチベーションが眠っている」という前提を持つことが重要です。
「当事者として体験したことはなく、見たり、人から聞いたりしただけ」といった知識しかない「未知のゴール」が「本当に自分らしさに沿っている価値かどうか」は、当事者として体験しない限り本当の吟味はできません。実際に味見した後でしか、有意義な判断はできないのです。世間で「成功」とされている価値観も、実際には誤解や表面的な評価が含まれていることがあります。本物の喜びや、本物の問題解決につながっていない場合も少なくありません。
確実な道は「自分らしい成功の基準」を持って、それを強化していくことです。
気になることや、興味/関心のあるコトやモノは、すべてゴールの候補としてどんどん投げ込み、アンテナを立てることから始めましょう。やりたくないことに集中したり、やりたくないことを避ける努力はやめて、Want toに焦点を合わせることが大切です。情報/知識を積極的に取り入れ、そこから広げ確立していきましょう。
すでに明確なゴールがある場合は、その人生カテゴリーにおいて切実な思いを持ち、知識や経験を重ねてきた証拠ともいえます。その場合は、人生を俯瞰するツールを使って、現状のゴールの枠を超えてほかのカテゴリーにも目を向けてみましょう。新たな視点を取り入れながら、ゴールを更新することをおすすめします。
ここまでの内容を確認したら、各カテゴリーごとに、「夢、やりたいこと、興味、関心(Want to)」を、3つ以上書き出してみましょう(4-1に記録)。
スキル3と同様に、スキル4の視点も日常的に意識しながら、強いゴールへと育てていきましょう。ここまでの作業で、3-1と4-1に、あなたのゴールに関するテーマを合計6つ、言語化できたはずです。
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
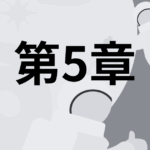
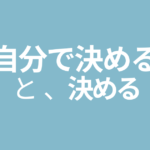
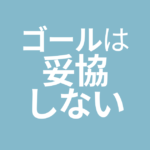
![[3-1] 自問自答で夢を深掘り](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/3-1-300x158.png)
![[5-4] 「限界突破への不安」をチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-4-300x158.png)
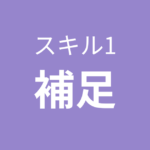
![[1-3] 1-1の真逆のポジティブ状態は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-3-150x150.png)
![[1-9] 1-7(と1-8)を小箱へ入れる](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-9-150x150.png)
![[2-0-1-2] 超ポジティブの要素も加える](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-0-1-2-150x150.png)
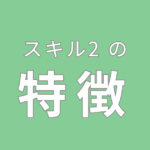
![[2-0-1-1]超出世の要素を加える](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-0-1-1-150x150.png)
![[1-5-2]課題を解消させる「価値」は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-5-2-150x150.png)