この記事でわかること:「自分で決める」から、モチベーションが向上する
- ゴールの領域を広げれば主体性につながる
- 本音を大事にすれば、モチベーションは枯れない
- ゴールに妥協せず、もっと多くを望んでいい
結果が出やすい人
5つ目の応用です。
第1章で、「結果が出やすい人は自分へも他人へも加点評価ができる人」と定義して、下記のような特徴を挙げました…
・フットワーク軽く、地に足が着いている
・自己評価が高く、達成のプロセスを楽しんでいる
・ゴールを持ち、自分のペースを守る
・理解者や協力者がまわりにいる
・自然体でリラックスしている
認識、思考、感情、行動が「自分のやりたいことや、ゴールの価値」に向かって一致していて、モチベーションが保たれ、行動もつづきやすい状態のことです。
アファメーションの活用で未来のゴールがより身近になり、モチベーション活性に役立ちます。達成の瞬間を目指すだけでなく、成長や学びのプロセスそのものが楽しい、という体験になるものと思います。
自分の価値基準を体現できてくると、物事の優先順位をつけやすくなるし、周囲を尊重しつつも自分のペースを保ちやすくなるでしょう。大きな成果だけに固執するのではなく、地に足のついた小さな行動を積み重ねられるようにもなるでしょう。本音と建て前などの自己矛盾が減るため、人間関係もより良いものになっていくものと思います。
その頃には、「自分にはできる」「できている」「未来もできるはずだ」という自己評価が、今よりも多くなるはずです。また、他人への評価も高まり、誰かを応援するのも応援されるのも、もっと自然なことになってくるでしょう。
自分で決めたゴールがあり、他者を(良い意味で)巻き込みながらゴールに対して加点評価ができ、達成への段取りを楽しみながら、認識/思考/感情/行動がゴールに向かって一致する状態は、本メソッドが目指すものです。
360度自分で決めると、「お宝」が
結果の出やすさを支えるほかの要素としては、ゴールを360度自分で決めることです。
「今やっていること以外は、自分の仕事や役割ではない」と思い込んでいることがないか、整理してみましょう。たとえば…
・今はほかの誰かがやってくれるから、自分はやらなくて済んでいる
・でも、本当は自分もやった方が楽しく、喜びかもしれない
・できた方が、人生が豊かになるかもしれない
・それが自分だけでなく、周囲の人にもプラスになるかもしれない
こうした可能性を考えずにいると、新しい経験や出会いの機会を逃しているかもしれません。それは損です。「やりたい」「関わりたい」気持ちがあるなら、その領域をゴールの範囲に加えてみましょう。やることはシンプルで、「ゴールに決めて、イメージに加えるだけ」です。
結果に対して効率だけを考えるなら人に任せた方が良い場合もありますが、ここで言いたいのはマインドのお話です。「自分には関係ない」と決めつけ、無視・無関心でいてしまうと、その領域にある価値を放置することになり、もったいないことです。
この決めつけには、思い込みや情報不足が関係しています。「そこにお宝(価値)が眠っているかもしれない」という前提を持つだけで、変化のきっけかが生まれます。その方がずっと良い選択をしやすくなるのです。少し意識を変えるだけで、その先の結果が変わるかもしれないのです。もし、自分の本音とズレている部分があるなら、うまくやっているつもりでも、実は本質的な価値から遠ざかっている可能性があります。
ゴール設定は「素の自分」から始める
「素の自分」に向き合うだけで始められるのが、ゴール設定です。
次のことが体験として理解できてくると、本書をさらに活用できるでしょう…
・より良い価値へ向けたゴールを設定しつづける
・ゴールの抽象度を高めつづける方向を目指す
個人が「より良さへむけた価値」を追求すると、それが他人や社会、地球のためにもつながるため、ゴール設定はポジティブで清く正しい良い行動になります。
ゴールの抽象度を高めるためには、抽象度の高い人の話を聞く、本を読む、実際に体験したりを積み重ね、体系的な知識を広げ網羅していくのが近道、ともお伝えしてきました。
私たちは、生まれたときから「ヒトを真似ることで人間になった」ので、さらなる成長を目指すなら、同じ方法を活用するのが合理的です。ただし、単に権力の顔色をうかがうだけでは、自分らしさからは遠ざかることになります。そうすると、動きが鈍くなり、納得感のある結果を得るのも遅くなってしまいます。
妥協せず、ポジティブなゴールを設定しよう
どの時点でも、「やりたいこと」には白黒をつけ、ポジティブなゴールを人生の広い視野で設定しましょう。
こんな人はいないでしょうか…
・仕事中はモチベーションが低いのに、遊びに行くと別人のように元気に
・上司として尊敬されてはいないが、趣味では超人的な才能を発揮
ありそうな話ですが、どこかの分野で結果を出せる人は、実はほかの分野でも結果を出せる可能性が高いものです。
あなたも「これでいいや」と妥協している分野はないか、チェックしてみましょう。本気を出さない理由があるのかもしれませんが、もっと多くを望んでも良いのです。
逆に、仕事で優れた結果を出している人が、無趣味で悩んでいることもあります。夢中になれる趣味は、たまたま、まだ見つかっていないだけかもしれません。多くの場合、すでにやってきている、とか実はいつもやっているのに「当たり前すぎて気づいていない」「無意識すぎて発見していない」という状況なのかもしれません。子どもの頃に何が好きだったか、念入りに思い出してみましょう。
苦手意識にも挑戦
多方面で卓越的な結果を出しても、特定の分野だけ大の苦手、という人もいるかも知れません。
苦手で不得意なことがあっても「得意を伸ばせばそれで良い」という考えもありますが、セルフコーチングでは特に、それが良いとも悪いとも言いません。
ただ、不得意というより「苦手感」とか「苦手意識」の問題なら、セルフコーチングを実行して「価値が突き抜け最高に到達して、溢れてしまって、横にまで広がったその結果」→「苦手を克服したい!克服が楽しい!と自発的に思える」ようになる可能性は、あります。苦手感や苦手意識がセルフイメージを下げている原因であるなら、「克服のためのモチベーションや行動が自然に湧いてくる」こともあるでしょう。ゴールを高めつづけて、自分の限界を自然に広げるのが本メソッドの趣旨です。
自分で自分をリードできる
誰かの背中を追いつづけるだけでは、自分らしい価値は見つかりません。大切なのは「自分で自分をリードする」ことで、それも本書の趣旨になります。「自分を最愛の人として真摯に向き合って、大切な時間をポジティブで生産的な選択に使い、行動しやすい環境をつくる」それが、成長、達成、学びのプロセスを楽しむ生活になります。
🔹 前のページ:「人生のゴール…」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
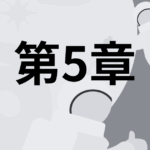
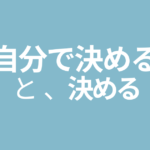
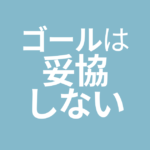
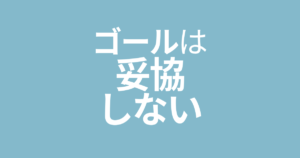
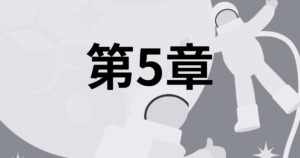

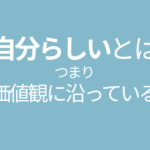
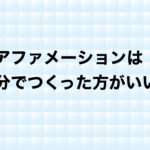
![[6-11] 物語のクライマックスは?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/6-11-150x150.png)
![[1-12]メッセージ](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-12-150x150.png)
![[2-0-2]限界突破ゴール仮設定](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-0-2-150x150.png)
![[1-11] 新しいセルフイメージ](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-11-150x150.png)
![[5-1-5]達成場面/エピソードは?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/06/5-1-5-150x150.png)