この記事でわかること:人生の軸となるゴール設定のヒント
- 統合ゴールとは、深い価値観と結びついた人生の根源的な目標
- 自分のWant to(やりたい)が恐怖を超えるとモチベーションが保ちやすい
- 過去の経験や問題意識が、人生のゴール(統合ゴール)を見つける鍵
統合ゴールとは、人生の本質的ゴール
4つ目の応用方法です。
人生のさまざまな分野でゴール設定をつづけていくと、ゴールに関係する概念の抽象化が進みます。価値がひとつの大きな概念へ向かってまとまっていきます。その先に存在しているのが統合的ゴールです。人生のゴールともいえるものが見つかると「これだ」と、直感的に確信できる瞬間が訪れるかもしれません。まるで、パズルのピースがすべて揃って、しっくり腹落ちするような感覚です。
スキル6では、価値を発見するプロセスを扱いました。
統合ゴールとは、特に本質的で深いモチベーションと結びついたゴールのことです。抽象度が高い価値だからこそ、多くの人と共有/共感できる価値を持つことが特徴です。ただし、統合ゴールの表現は、知識や経験が増えるにつれて更新されていきます。
避けたい価値でもOK
また、統合ゴールは、ポジティブな価値だけでなく過去のネガティブな経験から生まれる場合もあります。そんな「避けたい価値/ネガティブな価値」が動機であっても構いません。
見つけるヒント
一生かかっても達成できないような大きなゴールであるほど、モチベーションや情熱がつづきやすいものです。統合ゴールは、自分自身で見つけるのが理想ですが、そのヒントを解説します。
世の中には、誰もが心を痛める問題や課題が数多く存在します。メディアをくまなくチェックすれば、悪いニュースばかりが目に入ることもあるでしょう。
ですが、実は多くの人が、すでに「自分にとって重要な問題」を体験的に知っています。たとえば過去に、次のような経験があるかもしれません…
・過去にネガティブなトラブルに巻き込まれたことがある
・直接巻き込まれなかったが、目撃したことがある
・誰かから、その出来事や経験について詳しく聞いたことがある
こうした経験が、統合ゴールと深く関連している可能性があります。統合ゴールは、まったく新しいものを探すというよりは、「すでに体験的に知っていること」や「当事者として経験したこと」などのネガティブ事象にヒントがある場合が多いでしょう。
下記のようなポイントに注目しても、統合ゴールのヒントになります…
・現在進行形の個人的な課題や問題(ネガティブな事情)
・長年かかえている慢性的な悩み
・すでに過去の出来事だが、思い出すと嫌な記憶がよみがえる
これらの原因を「マイナスの価値」と仮定した場合、次のような視点が統合ゴールに近いでしょう…
・そのマイナスの価値が社会(地球/宇宙)から完全になくなる未来
・その課題(問題)解決に、自分が直接貢献すること
ただし、これらはあくまでヒントです。「自分のゴールと関連の深いマイナスの価値は何か」を意識しながら日々過ごし、スキル1~2を活用して不要な思い込みを手放していくことで、やがて「これが自分のゴールだ」という確信へ変わっていくでしょう。それは、自分を制限していたブレーキが弱まり、この問題(課題)解消に向けてモチベーションも高まり、自分に思いに素直に従って行動するようになってくる頃です。それは、「正義だから」「良いことだから」といった理屈ではなく、「ただ純粋にそれをしたい」という動機や、シンプルな「思い」です。
探す手がかり
さらに、統合ゴールを探す手がかりとして、「もしこの問題がなくなったらうれしい」と思える社会的課題を考えてみるのも有効です。たとえば、次のような問題がなくなった未来を想像してみてください…
(あいうえお順)いじめ、育児放棄、飢餓、格差、環境破壊、飢餓、虐待、孤独、ごみ問題、事故、自死、差別、戦争、人身売買、大気汚染、テロ、ハラスメント、貧困、売春、紛争、ハラスメント…
自分が経験をしたこと、直接見聞きしたこと、または強く問題意識を持っていることを振り返ってみましょう。自分ひとりの力では一生かかっても解決できないかもしれないが、達成できたら心からうれしいことは何か?を考えてみましょう。
また、統合ゴールは、必ずしも「マイナスの価値をなくすこと」に限定する必要はありません。「プラスの価値を増やす視点」で統合ゴールを設定することもできます。
統合ゴールは、一度みつけたら変わらない
統合ゴールの価値は、一度見つければ変わることはありません。ただし、統合ゴールが見つかった後も、自分の知識や経験が上がるにつれ、同じゴールでもその表現の範囲は変わっていきます。
統合ゴールが定まって、それに意識が向くようになると、価値の抽象度が高まり次のように変わっていくでしょう。
・「やらされ感」が減り、「やりたいからやっている」という感覚に変わる
・モチベーションが持続し、行動がスムーズになる
・無理や我慢をすることが減り、自然体で取り組むことが増える
見つけると、モチベーションに役立つ
たとえば、仕事に対して以前は「やらなければいけない(Have to)」と感じていたことでも、自分の大きなゴールと会社のゴールが入れ子のように重なって「主体が逆転」すれば、個人的なモチベーションは回復していきます。
やらされ感が減る方向
気が進まず「やらされている」と感じていたことでも、「Have to感」が減り「やりたいからやっている」という感覚になってきます。自分が主体になることで目の前の仕事と自分のゴールが結びつき、関係性が強くなります。ゴールの価値に関する情報が見えやすく聞こえやすいため仕事への関心が高まり、視野が広がり興味の範囲も広がるのです。この間も、無理や我慢は減り、自分らしさを保ったまま自然体で取り組むことが増えるでしょう。
「Want to」が「恐怖心」を上回るまで
スキルを活用することで、一時的に感情の波は起こることがあります。これは、意識と無意識の間を行ったり来たりする過程の一環で、モチベーションを改善するためのものです。その過程では、ときに無理や我慢をすることもあるかもしれませんが、それは最終結果ではありません。大切なのは「無理や我慢をしなくてもWant to(やりたい)という気持ちが恐怖心を上回る状態」へとズレていくことなので、その状態を目指してスキルを繰り返し活用しましょう。
会社のゴールを超えて、大きく設定しよう
また、会社のゴールよりも、個人的なゴールを大きく設定することをおすすめします。
個人のゴールを拡大することで選択肢が増え、責任感が増し、より「人生の主体は自分」だと実感できるようになります。その結果、仕事へのやりがいも増していくでしょう。
もし、仕事を辞めたいと思ったときは、感情のままに判断するのではなく、まずは会社のゴールよりも自分のゴールを上げ(拡大し)て設定し、それからの判断にするのが得策です。より自分が望む方向へと進む可能性が上がります。仮に、別の会社に転職したとしても、することは同じ「自分のゴールを育てる」こと。それを今の環境で始めるのか、後で取り組むかの違いにすぎません。また、本書の方法で自分のゴールを育てるなら、自己評価も他者からの評価も下がることはなく、むしろ向上するのではないでしょうか。
真のゴールの種は、心の中に眠る
統合ゴールの抽象度を高めていくには、個人的なネガティブ経験や、現在の課題/問題を整理し、それを糧にするのが効果的です。確かに、ネガティブな部分に向き合わず見て見ぬふりをしている方が楽で、簡単な道には見えないかもしれません。ですが、その過程で「余裕が生まれる」→「モチベーションが増す」という流れがあって、それが無理なく前に進む力となるのです。モチベーションが増えてくる状態とは、常に「その先」に魅力的なゴールやビジョンが描けている状態です。
スキル1~6のサイクルが繰り返されることで、未来のビジョンやその先のゴールが、より身近になります。ポジティブな認識/思考/感情/行動が増えると、恐怖心よりもWant toが上回っていき、統合ゴールに向かって思わず動き出したくなるときがくるものと思います。
頑張らない、ムリもしないで
頑張るのでなく無理をするのでもなく、Want to(やりたい)気持ちが恐怖心を上回るまでを目指し、実践をつづけることをおすすめします。
重要なのは、人と比べるのではなく、自分らしい考え方/自分らしい感じ方/自分らしい方法で、自分自身に挑戦していく道です。「できない」「やりたくない」と少しでも感じるものは、ゴールに含める必要も、無理をする必要もありません。
🔹 前のページ:「”その先”にゴ…」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
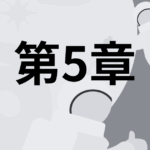
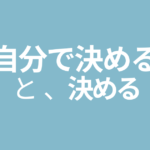
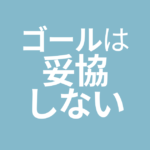
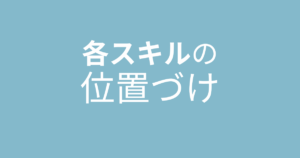
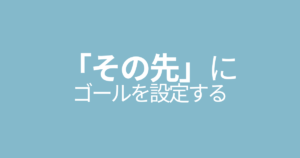
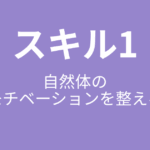
の補足](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/08/3-1の補足-150x150.png)
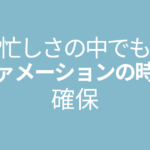
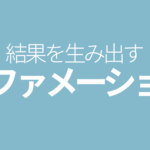
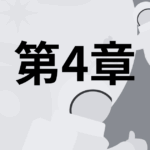
![[6-13] 未来を現在に反映](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/6-13-150x150.png)
![[2-16] 価値のとりこみ](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-16-150x150.png)
![[1-14] 自己評価](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-14-150x150.png)