ゴール5-3への「自分の反応」をチェック
「ゴール5-3」は不安?不快? or 不安も不快もゼロ?
資源合成5-3で、ゴールのボリュームが増し絵(映像)がより鮮明になり、人によっては、以前よりもゴールが怖ろしく感じられたり、圧倒される印象に変わることがあります。また、合成の過程で不安や不快感が湧いてくることもあるかもしれません。
もし今の時点で、怖さや不安、不快感がまったくない場合は、5-4の「不安なし」にチェックを入れ、5-5へすすみましょう。モヤモヤ・違和感程度でも5-5へ進んで問題ありません。
一方、ゴールに対して怖ろしさや不安、不快感がある場合は、次の「~ゴールが不快/不安なときにすること~」を、つづけて読んでください。
ネガティブ感情が湧くこと自体は問題ではなく、むしろ、「ゴールに対する思いや、感情が強まった」証拠で、適切に設定されています。ゴールの臨場感が高まれば、それだけ限界突破に効果的です。圧倒されるほどの強い臨場感があるほど、行動を起こしやすくなり、実現しやすいゴールです。
ただし、そのまま何もしないと、以下のようなリスクが残ります…
・ポジティブではなくネガティブ(不安)が実現したと勘違いする
・ゴールに対して足踏みしてしまう
・(本書の)スキル実践から遠ざかる
・ゴールについて考えるのをやめる
・踏ん切りがつかない
・勇気が挫ける
これらについては今後も、常にセルフチェックが必要です。そして、これらを防ぐために、次の解説を参考にしながら適切に対処しましょう。
ゴールが不快/不安なときにすること
ギャップを意図的に設定したり、資源を合成したりする際、自分らしさとは異なる価値観が混じっているため、絵や映像が不快に感じるのは自然なことでしょう。
また、設定したゴールが怖く感じたり、限界を突破すること自体に不安を覚える場合は、スキル1~スキル2つづけて(31ステップ)か、スキル1のみ(14ステップ)を活用できます。基本的には、スキル1~スキル2まで31ステップひと続きで使う方が効果的です。ですが、もしスキル2までは必要がなく、スキル1だけで十分だと判断できる場合は、スキル1単体(14ステップ)だけの活用で終えても構いません。
スキル2の活用は、実践するタイミングや頻度を選びます。スキル1だけでなく、スキル2も「できそう」「やりたい」と思えたときに、両方活用すると良いでしょう。最終的には、自分の判断で決めてOKです。ただし、スキル1や2を実践の前後で、不安や不快感がどれだけ変化したか、振り返りが必要です。
・ゴールの絵(映像)の特徴
・「何が」「どのように」「なぜ」不安なのか/怖いのか
などを事前に詳しくメモしておくと、後で効果を評価しやすくなります。効果を振り返る機会を設けることで、結果への確信や信頼感も高まります。
スキル1単体(14ステップ)、またはスキル1〜2(31ステップ)を実践し、自分の「真ん中」に戻ったら、5-3のメモをもとにゴールの絵(映像)を再び想像し、プロセスを再開します。
恐怖や不安など、不快な感情が減るということは、感情の強さが和らいだということですが、ゴールの臨場感が下がるわけではありません。ネガティブな重さが取り除かれることで、ポジティブな未来の絵(映像)の合成がスムーズになり、臨場感も湧きやすくなるでしょう。
ゴールのイメージに新たな合成を加えるほど、ゴールの密度が高まります。ここで言う「ゴールの密度」とは、情報量や抽象度の高さを指します。「想像を越えた」未来の姿をゴールにするのが目的なので、細部までリアルに想像できなくても大丈夫です。ぼんやりとしている大まかな絵(映像)のまま進めても問題ありません。
限界突破への不安とは?
5-1-2で前述した、限界突破に効果的なゴールのレベル感は下記の通りです…
・現在の自分とは大きなギャップがある(驚異的な成長が必要)
・腰が抜けそうなほど並外れているが「Want to」である
・身震いするほど怖ろしいが、心からやりたいこと
・「未知」や「未経験」の領域への冒険
・出世や挑戦の度合いが極めて高い
やりたいことであり、望んでいることであっても、私たちは本能的に「現状からの変化」を怖れるものです。本当に実現することが、「うれしい」と感じる一方で、同時に、「不安」や「怖さ」も同時に湧いてきます。「もしも本当に実現してしまったら、どうしよう」「自分が変わったら、周りの人との関係性はどう変わってしまうだろう」など、気になる人もいるでしょう。
心理学者の中には、「不安は、ただの興奮だと捉えよ」とアドバイスする人もいます。これは、単に神経が高ぶっているだけだよ、という意味です。実際、すでにそのゴールに相当する現実やセルフイメージを「当たり前」のものとして生きている人も大勢いますし、実現することで得られるのは良いこと/ポジティブな変化だけです。素直にうれしいし、行動や能力に対する自己評価も高まり、ポジティブな感情も増していきます。そして、あなた自身の変化、そして在り方や存在自体が周りの人や社会への貢献にもつながることでしょう。
勇気を持って、現在の自分と大きなギャップのあるゴールを設定(決意)するとき、「こんなゴールを持っていいのだろうか?」「自分にはふさわしくないのでは?」「本当に達成できるのか?」といった不安や疑いが顔を出すのも自然なことです。
ですが、仮に達成できなかったとしても「現状に(もとに)戻るだけ」なので何か悪いことが起こるわけではありません。「こんなゴールを持っていいのか?」という疑念に対しては、「自分はこのゴールを持つのにふさわしい」と、自分で決めてしまいましょう。「本当に達成できるのか?」という不安にも、実際やってみてどうかは別として、達成する、と「決める」ことに尽きます。取り組む中で、達成までのプロセスは楽しいものになるしょう。なぜなら、達成できる頃は「できて当たり前」というセルフイメージに変わっているからです。達成の瞬間だけではなく、できなかったことがひとつひとつ「できている」と思えるようになっていく過程は、確実に楽しいのです。
未来に何が起こるのかは誰にもわかりません。だからこそ、自分の「意図」と「選択」にかかっています。
不安のメリット
私たち生き物は、不安や恐怖心のおかげで、安全を守りながら生き延びることができています。現在の自分が脅かされるほどギャップあるゴールを決断するときも、不安になることで自身を守るのです。この不安は、「挑戦的でやりがいのあるゴールを目の前にしたときの、応援のシグナル」と捉えることもできます。
適度な緊張感があるほうが、パフォーマンスが高まり良い結果につながることは、よく知られています。逆に、不安がまったくなければ危機感がなくなり、たとえば平気で赤信号の横断歩道を無防備に渡ってしまうかもしれません。前述のように、不安=ただの興奮と捉えることもできます。もし、不安がただの興奮だとすれば、それは「やる気の一種」「自立心の現れ」「強さの証」とも、解釈できるでしょう。
つまり、不安は決して悪者ではありません。
ゴール設定との関係で考えると、ゴールを決めた後に湧き上がる不安は「良い変化の前触れ」と、捉えることができます。そう考えると、不安の中にも誇らしさや楽しさが加わり、少し安心感を持てるようになるでしょう。
不安のデメリット
緊急時に必要となるような強い恐怖心(災害や事故など)は日常的に頻繁に起こるものではありません。ゴールを設定するうえで想像力は重要ですが、不安が顔をだすと視野が狭くなり、ポジティブな想像力が働きにくくなったりもしてしまいます。
限界突破への不安を感じたときは、その不安を課題にスキル1(14ステップ)を単独で使うか、スキル1~スキル2の両方(32ステップ)を使って対処が可能です。
また、「不安になること自体への不安」や「恐怖心を抱くことへの不安」が現れる場合もあるかもしれませんが、「不安だ」と気づいた時点で、スキル1や2は同じように役立ちます。
🔹 前のStep:「[5-3] ゴールの…」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
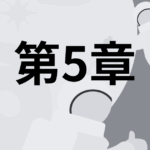
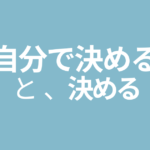
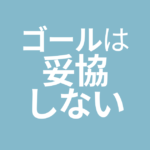
![[4-1] 人生の価値を最大化](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/07/4-1-300x158.png)
![[5-3] ゴールの絵に「資源」を合成](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-3-300x158.png)
![[5-1-1]ポジティブかつ臨場感の高いゴール](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-1-150x150.png)

![[6-13] 未来を現在に反映](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/6-13-150x150.png)
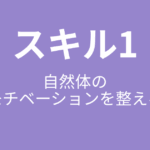
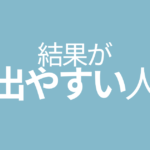
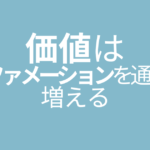
![[2-7]1-7~2-6自己像を客観視](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-7-150x150.png)
![[4-1] 人生の価値を最大化](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/07/4-1-150x150.png)