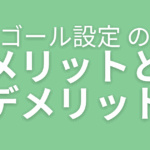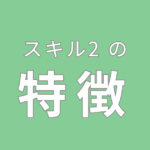この記事でわかること:不安は扱い方次第
- 不安はゴール設定に伴う自然な反応で、成長の前兆でもある
- 不安は「原因のある不安」と「漠然とした不安」分けて考える
- 不安に気づけること自体が、抽象度の高い思考ができている証でもある
・・・
📘スキル1〜6を繰り返していると、意図と結果とが一致することが増えるでしょう。未来のゴールのイメージに慣れていき、「こんなはずじゃなかった」が減り、「予想した通り(望ましい)結果になった」という認識場面が増えてくるでしょう。
これは、ゴールに関する抽象的思考が増えた、という証で良い変化です。ただし、一方で注意すべき点もあります。それは、「未来への抽象的思考が増えると、不安への想像力もたくましくなる」ということ。知識や経験が増え、未来を予測する力がつくことで、同時に不安をさらに呼び起こしやすくなるのです。ゴールは望ましい変化をもたらしてくれますが、本来、私たちは変化を警戒する生き物です。そのため、ゴール設定によって不安が身近になることもあるのです。
また、本書のテーマはモチベーションであり、意図的に感情の変化を生みだすもので、変化に対して不安が生まれるのは自然なことです。その不安を有効活用するためにも、あらかじめ適切な対処方法を把握しておきましょう。
本書では、不安を2つに分類し、それぞれに適した対処法を解説します。
「具体的な不安」と「漠然とした不安」
1,具体的な不安感情
・限界突破(変化)に対する不安
・ゴールを決断することへの不安
・未来のセルフイメージに関する不安
などの、具体的原因のある不安感情
2.漠然とした不安感
・未来についての抽象的思考が高まった結果、なんとなく感じる不安
・明確なきっかけや理由がなく、膨らんでくる不安
どちらかといえば、未来の可能性を考えることで生じる不安です
🔹 前のページ:「効果…自己評価」へ ◃ 戻る
© 2025 Ando Mayumi|転載・複製禁止|引用時は出典を明記|「源泉モチベーション」は登録商標です
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
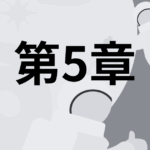
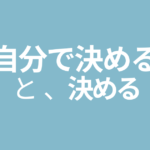
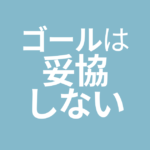
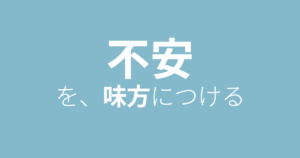

![[6-6] ゴール体験での五感情報は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/6-6-150x150.png)
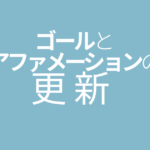
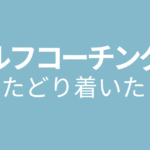
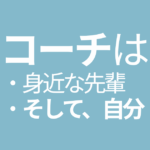
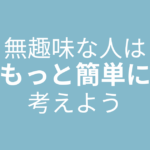
![[2-15-2] 思い込みをプラスへ転換2](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-15-2-150x150.png)