この記事でわかること:脳の使い方を変えて道を開く
- 前頭前野を使うことで、扁桃体の反応を逆手に取って活用する
- 本書のスキルは、前頭前野の機能を意識的に活性化する実践(特に5と6)
- スキルは無理せず、やりたいものを日常に自然に取り入れればOK
不安や恐怖の感情はこうして生まれる
不安や恐怖の感情は、脳の扁桃体という領域が担っています。扁桃体は、「快/不快」「安全/危険」などの価値の程度を判断し、私たちの生存を守る役割を持っています。「不快」や「危険」の判断は、一瞬のうちに下されます。理性的に考えている間に、危険から逃げ遅れてしまうからです。偏桃体は、これまでの記憶をもとに、無意識的に危険を判断します。たとえば…
・「以前、こんな場面で危険な目にあった」
・「この状況はそのときと似ている」
・「勝てそうなら戦え、無理なら逃げろ」
というように、直感的でアバウトな判断をします。偏桃体の判断は必ずしも正確ではありません。
偏桃体と前頭前野の役割の違い
扁桃体は「考えない脳」であり、意識的で知的な判断はしません。意識的で知的な判断をしているのは、前頭前野という領域です。
前頭前野は、脳の最高中枢と考えられていて、人間らしさや社会性に深く関わる部分です。脳の働きは全て解明されているわけではありませんが、前頭前野には次のような働きがあることがわかっています。
《前頭前野の主な役割》
・思考や感情を客観的に観察
・感情のコントロール
・意識的な判断
・未来の計画
・抽象的思考
・論理的思考
・理性的思考
・概念整理
・目標設定
・共感性
・やる気
本書のスキルの中身は、これらの前頭前野を活性する作業に当たります。
偏桃体 vs 前頭前野
扁桃体は、感情を拡大する働きを持っています。記憶の価値を「ネガティブ」と判断すると、ネガティブな感情を強調し、拡大してしまいます。扁桃体活動が優位だと感情的になりやすく、前頭前野の働きが低下します。逆に、前頭前野が活発に働いているときは、扁桃体の活動を抑えることができます。
つまり、偏桃体は過去の記憶に雑に反応し、不安や恐怖を自動的に大げさに拡大する傾向があります。この扁桃体活動を抑えるには、「前頭前野活動の働きを意図的に活性化させる」必要があります。
そのための効果的なのが、本書のスキル実践です。スキルを実践することで、偏桃体は「未来のゴール」という「ポジティブな記憶」に反応し、ネガティブ感情ではなく、ポジティブな感情を拡大してくれます。
≪ポイント≫
・上記の《前頭前野の主な役割》を、「そのために時間を割き」「意識的に」「わざと」始めることが不安などのネガティブ感情の扁桃体活動を抑え込むカギ
・上記の《前頭前野の主な役割》とは、本書のスキル1~スキル6の中身そのもの
・偏桃体のネガティブ反応を覆すのに特に効果的なのは、スキル1~6の中でも、よりポジティブな未来の記憶を扱うのがスキル5やスキル6
無理なくできる実践方法
ただし、スキルを「~しなければ」という気持ちで、義務的に実践するなら逆効果です。
状況によっては、スキル1(14ステップ)もスキル1~2(31ステップ)も、実践できないこともあるでしょう。たとえば…
・仕事中や外出先で、まとまった時間がとれない
・手が離せず、集中するのが難しい
このような場面でのスキル実践は現実的ではありませんし、そうこうしているうちに、偏桃体が役割を遂行し、不安感が成長してしまう可能性があるので、前述の「3分間行動で応急処置」が必要になってくるのです。
次で長期で不安を予防する方法の説明もありますので、「できそう」かつ「やりたいもの」は、日々意図して取り入れていくことをおすすめします。
🔹 前のページ:「漠然とした不…」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
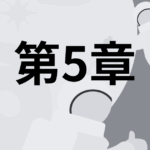
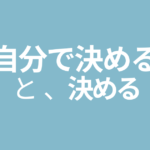
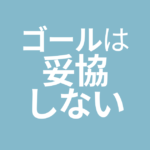
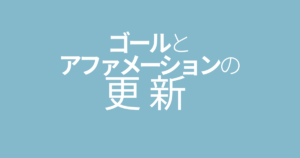
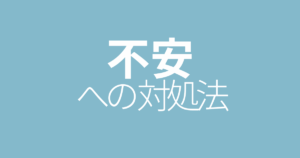
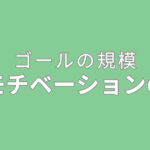
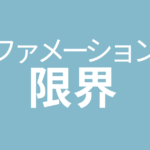
![[2-3] そのネガティブ感情はどこにある?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-3-150x150.png)

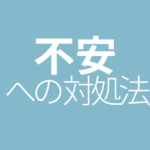
![[2-9-2] 悪影響人物にとっての価値は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/コーチングスキル2-9-2-150x150.png)
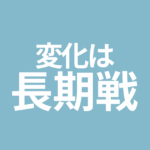
![[5-1-2] 5-1-1の中でも怖いゴールは?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-2-150x150.png)