実用的でない不安は、数値化と3分間行動で整えよう
- 実用的でない不安を放置すると、生産性が落ちる
- 落ち着いた環境があれば、不安を数値化しシンプル行動で整える
- 時間がないときは、3分でできる応急処置8選から対処を試せる
📘「2.の漠然とした不安感」への対処法を解説しますが、まずは、不安がそもそもなぜ生じるか?整理してみましょう。
【不安感の根源とは?】
不安感の根源を突き詰めると「飢え」「猛獣に襲われる恐怖」などの生存本能に結びついていると思われます。
・「飢え」は、現代では実質克服されている
・「猛獣に襲われる恐怖」も、普通に生活していればほぼ無縁
科学肥料が発明されているため、政治的問題を別とするなら食料不足は克服されているという見方もあります。先進国での大量食料廃棄の問題もなくなってはいません。市街地の建物内で暮らして、森の奥へ自ら分け入らない限り、蛇や熊に襲われる危険もほぼありません。つまり、不安感は「有事のためのもの」や「有事に備えるためのもの」であって、本書のスキルのように想像力しか使っていないときに実用性は低いものです。頭の中で生まれた不安は、実際的な危険ではないということです。
【漠然とした不安感とは?】
2.「未来についての抽象的思考が高まった影響で起こる、漠然とした不安感」は、雲のように捉えどころがなく、どこからともなくいつのまにか現れます。明確な原因があるようでないような、ないようであるような不確かな感覚です。気づかないうちに広がり、影響を与えます。
【漠然とした不安感を放置すると】
こうした漠然とした不安感を放置すると、視野が狭くなり無意味な行動を繰り返したり、判断を間違うこともあります。結果として生産性が低くなります。不安感は時間がたてば自然と消えることもありますが、その間に時間とエネルギーを失ってしまうのはもったいないことです。
漠然とした不安感が生まれていると気づいたら、次のページの「不安を数値化して対処(時間がとれるときの対処①)」の方法で、早めに白黒をつけましょう。余計な消耗を防ぎ、時間を有効活用するためです。
►5~10分の時間が確保できる場合の対処①
【ひとりで落ち着ける環境で10分間の対処】
「不安を数値化して減らす」方法です。ひとりで落ち着ける時間と環境があるときに実践するのが理想的です。
・「極限の不安」を10点満点にした場合、「今の不安」は何点か?
・その不安を1点下げるとしたら、今、できることは何か?/何がしたいか?
このように、不安を数値化しながら具体的対処を考えることで、「すぐにできること」や「本当にやりたいこと」が見えていきます。この2つのプロセスを繰り返し、不安を0点まで下げていきましょう。
この質問で導き出されるのは、ハードルの高い解決策や複雑な方法ではなく、今すぐできるシンプルな選択肢が自然と思い浮かぶはずです。行動の選択肢というよりも、それ以前の、心の中を整理することに近いやり方です。
実際に解決行動をとることで、自分への信頼感や自己評価が上がる効果も期待できます。また、「できる/やりたい」などのWant toに基づく判断や行動が、前頭前野を活性
させ、不安をポジティブへ変換する助けになります。
►2~3分の時間しか確保でないときの対処法②
【不安を数値化して減らす時間がとれないときは「3分間で応急処置」】
スリルも味わいながら成長したいという人もいるかもしれませんが、不安感を放置すると膨らんでしまうことがあるため、早めの対処が理想です。必要時すぐ使えるようにしておきましょう。
事前に、下記8つの応急処置を試し、自分に合うものを1つ決めておくことをおすすめします。
《不安の応急処置 3分間行動8つ》
―――アファメーションを唱える…応急処置①―――
本書のゴール設定で手に入れたアファメーションは、ご自身のオリジナルで、ポジティブなゴールに直結する言葉です。結果につながりやすいことを考えても効果的です。口に出して何度かつぶやいてみましょう。
―――くつろぎのポーズ…応急処置②―――
社会心理学の研究からですが、「ビーチチェアでくつろいでいるような姿勢を」をとる、というもの。座り心地の良い椅子やソファに深くもたれかかり、足を高く上げ、首の後ろで腕を組む姿勢をとってみましょう。
―――その場を離れる…応急処置③―――
不安を感じるその場所から、一時的に離れます。逃げるが勝ちという言葉がありますし、気分転換にもなります。外出が難しい場合は、窓をあけて換気する、遠くの景色を眺めるなとも良いでしょう。
―――深呼吸でリラックス…応急処置④―――
太極拳やヨーガでも、「呼吸法は呼気(吐く息)を意識することが重要」とされています。リラックスとは、主に身体の脱力のことなので、ゆっくりと息を吐き切りながら身体をほぐしましょう。呼吸法は様々な指導があるため、自分に合ったものを選びましょう。
―――腸内環境を整える…応急処置⑤―――
プロバイオティクス(善玉菌)摂取で、マウスの不安行動が減ることが実験で確認されています。おすすめはビフィドバクテリウム・ロンガムですが、乳製品は体質に合わない場合もあるためご注意を。
―――ペンをくわえる…応急処置⑥―――
大臼歯で箸やペンをくわえると、大声で笑うときの「笑顔の筋肉」が動きます。そのまま2分間待てば気持ちの方がついてきて、不安でいることの方が難しくなります。
―――俯瞰的に自分をみる…応急処置⑦―――
自分を第三者の視点で観察してみましょう。「不安を抱える自分」を他人事のように眺めることで、適切なアドバイスを思いつきます。アドバイスを思いついたら、不安な自分にそれを伝えてあげましょう。別人になりきった視点で観察してみても、おもしろい結果になるでしょう。
―――やーめた、と口に出す…応急処置⑧―――
「不安、やーめた」と口に出して言ってみましょう。脳は、聞こえる音に必ず影響を受けるし、自分の言葉にも素直に反応するため、意外と効果があります。
【「3分間行動で応急処置」の後 → 時間が確保できたら「不安を数値化して減らす」を実践へ】
3分間の応急処置は、時間やひとりになれる環境が確保できないときのためのものです。その後、まとまった時間と落ち着ける環境が確保できたら「不安を数値化して…」を実践しましょう。不安に振り回されることはなくなるでしょう。
【そのほかの不安について】
そのほか、時間がありすぎると「暇」や「退屈」から不安感が顔を出すこともあります。人の思考はネガティブに傾きやすい特徴があるため、余裕のある時間がかえって不安を引き起こすことがあるのです。
こうした不安への対処法として「本書のスキルを実践すること」が効果的です。その理由については、次の「不安を味方につける考え方」で詳しく解説していますが、本書のステップを活用することで不安を中断し、脳をポジティブへ切り替えることができます。本書のどのスキルを実践しても、脳の特徴から見て合理的な方法になっています。つまり、難しく考えずに「自分がやりたいことをやる」という意識で過ごすのがポイントです。
🔹 前のページ:「原因のわかる…」へ ◃ 戻る
![[5-1-4] セルフチェック](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/5-1-4-150x150.png)
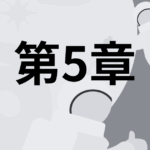
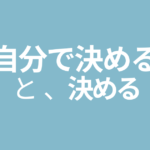
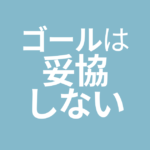

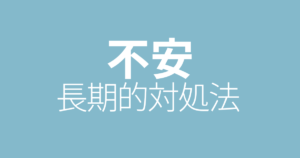
![[6-4] ゴール達成の自分になり切る](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/6-4-150x150.png)
![[2-17] 効果の自己評価](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-17-150x150.png)
![[1-5-1] 達成の条件/理由は?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/1-5-1-150x150.png)
![[2-0-1-3] ゴールをチェック①](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-0-1-3-150x150.png)
の補足](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/08/3-1の補足-150x150.png)
![[2-2] 納得度/リアルさの度合いは?](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/05/2-2-150x150.png)
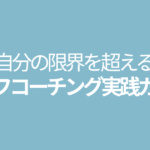
![[4-1] 人生カテゴリーの補足](http://anmicoach.com/wp-content/uploads/2025/08/4-1の補足-150x150.png)